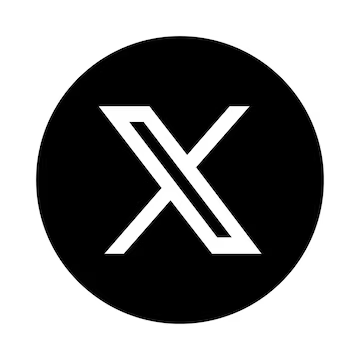本記事では旅館運営において経営者が抱える課題に対してシステム/DX化などの観点から解決方法を解説致します。
目次
旅館の現状と課題
ホテル数の増加や顧客ニーズの多様化、そしてコロナウイルス以降活発化するインバウンド需要などの厳しい状況に置かれ、価格面、人手不足、集客の困難と、経営に苦慮している施設も多く、旅館の軒数は減少傾向にあり、時代の変化に対応できていない課題があります。
それらの課題を一つずつピックアップして解説致します。
人手不足
旅館業界における人手不足は、長年にわたる課題で、深刻さは増すばかりです。背
景には、宿泊業全般に共通する要因として、長時間労働や不規則な勤務体制が敬遠され、若い世代を中心に就職希望者が少ないことが挙げられます。
また、給与水準が他業界と比較して低いことも、離職率を高め、新たな人材の確保を妨げる要因です。特に地方の旅館では、都市部への人口集中も影響し、深刻な人材不足に陥っているケースが多く見られますこのような状況に対し、国内の人材確保だけでは限界が見えてきており、外国人材の採用が注目されています。
政府も人手不足解消の手段として、宿泊業を含む特定の分野で一定の技能を持つ外国人を受け入れる「特定技能制度」を導入しており、2024年度からは5年間の受け入れ枠が大幅に拡大される ことも決定しています。これにより、これまで主に通訳業務などに従事していた外国人材だけでなく、フロント業務や客室清掃、レストラン運営など、より広範な業務での活躍が見込めます。
しかし、宿泊業における外国人材の受け入れ数は、他の産業と比較してまだ少ないです。制度の内容が複雑であることや、言語や文化の違いによるコミュニケーションの課題、受け入れ体制の整備など、外国人採用を進める上でのハードルも高いかもしれません。人手不足を解消するためには、外国人材の積極的な採用と同時に、既存の日本人従業員の労働環境改善も不可欠です。残業時間の削減や適切な残業代の支払い、ライフステージに合わせた柔軟な働き方の提供などが求められていくのかもしれません。
客室平均単価(ADR)の向上
旅館の経営において、客室平均単価(ADR)の向上は、収益性を高めるために重要です。
ビジネスホテルと比較すると、一般的に旅館は客室数が少ない傾向にあるため、RevPAR(販売可能客室あたり収入)を向上させるには、客室稼働率(OCC)だけでなく、ADRの引き上げが不可欠です。
日本人の国内旅行において旅館の利用はホテルに比べて少なく、理由として「価格が高い」「予算に見合った旅館がない」といったことが考えられます。これは、旅館が提供するサービスや施設に見合った価格設定ができていないか、あるいはその価値が顧客に十分に伝わっていない可能性が考えられています。
ADRを向上させるためには、単に価格を上げるのではなく、顧客がその価格に見合う価値を感じられるようにすることが重要です。そのためには、他の宿泊施設との差別化を図り、独自の強みを明確にする必要があります。例えば、地域ならではの食材を活かした料理、質の高い温泉、特別な体験プログラムの提供などが考えられます。また、ターゲットとする顧客層を明確にし、そのニーズに合致したプランやサービスを開発する ことも有効です。
さらに、WebサイトやOTA(オンライントラベルエージェント)における情報発信を強化し、旅館の魅力を効果的に伝えることも1つです。魅力的な写真や詳細な情報、顧客のレビューなどを掲載し、期待感を高めることで、価格に対する納得感を生み出すことができます。ホームページが見づらいといった課題を抱える旅館も少なくないため、情報の整理やデザインの改善もADR向上に繋がると考えられます。
オーバーツーリズム
オーバーツーリズム、いわゆる観光公害です。特定の観光地に観光客が集中しすぎることで、地域住民の生活環境や自然環境、観光資源などに悪影響を及ぼす現象です。
具体的な現状としては、近年、インバウンド観光客が急増している地域を中心に、交通機関の混雑、騒音問題、ゴミの増加、生活インフラへの負荷などが問題点として挙げられます。特に、歴史的な景観を持つ地域や自然豊かな観光地では、過度な観光客の集中が景観の破壊や生態系の悪化を招く懸念も生じています。
旅館運営においては、オーバーツーリズムは従業員の負担増加や顧客満足度の低下、地域住民とのトラブルといった課題を引き起こす可能性もあります。例えば、繁忙期の人手不足がさらに深刻化しスムーズに旅館の運営ができないことや、混雑によって顧客が十分にサービスを享受できなかったりするかもしれません。また、観光客のマナーの問題などが地域住民との間で不満を生じさせる可能性も考えられます。
課題への対策
積極的に新しい技術を取り入れ、業務効率化を図るとともに、変化する顧客ニーズに対応していくことで対応することができます。
DX化・システム導入
旅館運営におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)化とシステム導入は、人手不足の解消、業務効率の向上、顧客満足度の向上など、多岐にわたる効果が期待できる重要な対策です。
まず、ホテル管理システム(PMS)は、予約管理、顧客管理、客室管理、会計処理など、旅館運営の基幹業務を一元的に管理できます。これにより、手作業によるミスを減らし、業務の効率化を図ることができます。また、顧客情報の一元化により、きめ細やかなサービス提供やリピーター育成に繋げることも可能です。
自動チェックイン機の導入は、フロント業務の負担を軽減し、省人化に貢献します。特に、夜間や早朝など、スタッフが少ない時間帯でもスムーズなチェックイン・チェックアウトが可能となり、顧客の利便性向上にも繋がります。
複数のOTAや自社ホームページからの予約を一元的に管理するサイトコントローラーの導入は、予約情報の二重管理を防ぎ、オーバーブッキングのリスクを低減します。また、各OTAの空室状況や料金設定をリアルタイムで更新できるため、収益最大化にも貢献 します。
他にも、タブレット端末を活用した客室管理や従業員間の情報共有、AIを活用した問い合わせ対応、ロボットによる清掃など、様々なITツールやシステムの導入が可能であると考えられます。これらの技術を積極的に活用することで、人件費の削減、従業員の労働時間短縮、サービス品質の向上 など、多方面での効果が期待できます。DX化は、人手不足という課題を解決できるかもしれません。
HOTEL SMARTでは、宿泊施設の課題を解決し、さらなる顧客満足度の向上と、収益の向上を実現する宿泊施設向けオールインワンシステムです。
サービスの概要や導入事例、具体的な運用方法をまとめて資料をお配りしております。
ご検討のお役に立てれば幸いです。
観光立国としての観光地域づくり
日本が観光立国として発展していくためには、地域ごとの特色を活かした観光地域づくりが必要です。国は地方創生の起爆剤として観光産業に大きな期待を寄せています。2023年3月には「観光立国推進基本計画(第4次)」を閣議決定し、「持続可能な観光」「消費額拡大」「地方誘客促進」の3つをキーワードに、地方を重視した観光政策を推進しています。観光庁が発表している観光GDPを見ると、2019年には11.2兆円に達し、その中でも宿泊産業が21.9%と中心的な役割を担っていることがわかります。
しかし、日本の観光GDP比率は国際的に見るとG7の各国平均と比較して低い水準にあり、成長の余地が大きい一方で、宿泊業においては労働生産性や雇用者報酬の低さが課題です。このような状況を踏まえ、特に地域に根差した中小宿泊業においては、その現状や課題を整理しつつ、観光地域づくりにおいて中心的な役割を担っていくことが必要です。宿泊施設の主要な機能としては、宿泊の提供、飲食の提供、そして交流機能が挙げられます。
特に現代においては、個人化やリピーターが増加する中で、一対一のもてなしが重要となり、一旅館だけでなく地域全体で旅人と住民の交流の場を高めていくという地域経営も肝になってきます。宿泊施設は従来の快適な施設・サービスの提供という役割に加えて、地域を活性化する拠点としての役割を果たす可能性も考えられます。
例えば、ホテルや旅館内にフューチャーセンターを設置し、都市部と地方の人々をつなぐことで新たな付加価値を生み出す産業や地域特有の課題を共同で解決するきっかけを提供したり、観光客と周辺住民を結びつける「地域の共創の場」となることも期待できます。地域内の宿泊業者を中心に関連事業者・地域住民・宿泊客等がコミュニケーションを持ち、連携することで地域の強みを作り出し、宿泊業者自らがその強みの発信元になることが、地域全体の付加価値向上や発展に貢献すると考えられます。しかし、このような交流機能の発揮は、相応の規模や人材を有する宿泊施設への指摘と考えられ、中小規模で経営資源に余裕のない宿泊施設が単独で中心的な役割を担うのは難しいのが現状で、経営資源の制約から中小規模の宿泊施設が個別に地域全体の付加価値向上に資するような取り組みを行うのは難しく、地域全体を考える余裕がないのが現状です。
そのため、観光地域づくりにおいては、旅館ホテル組合や観光協会といった連携組織の活用が不可欠です。連携組織を活用する上での課題も明らかになっており、公平性やメンバーの意識改革などが挙げられますが、フューチャーセンターのように多様な人々が集まりアイデアを創発し実行していくことで、課題解決につながる可能性があります。
M&A
旅館業界においては、旅館の軒数は減少傾向です。これは、宿泊ニーズの多様化、価格高騰の影響を受け、旅館としての魅力が薄れていたり、時代の変化に対応できていないことが要因として考えられます。
宿泊施設の倒産件数は増加傾向にあり、新規の宿泊施設が増える一方で、倒産する施設も増え、新型コロナが落ち着いた今もなお、影響が残り経営に苦しむ施設を増加させる要因となりました。
このような倒産や廃業が相次ぐ現状において、M&Aは、経営が困難になった旅館が事業を継続するための有効な手段の1つです。特に、人手不足が深刻な旅館においては、M&Aによって他の宿泊施設や関連事業者の傘下に入ることで、人材を共有したり、効率的な人員配置が可能になる可能性があります。また、資金力のある企業による買収は、老朽化した施設の改修や新たな設備投資を可能にし、旅館の再生や付加価値向上に繋がることも期待できます。
おすすめの旅館向けオールインワンシステム
旅館運営の増収増益/業務効率化を実現するお宿奉行では自動チェックイン機や施設管理システム(PMS)、インフォメーションシステムのデジタルガイドなどをオールインワンで搭載し、自動化やコスト削減に貢献します。
オーダーシステムによるお食事時間のお伺いを自動受付できる機能やOTAの脱却と自社ホームページからの予約を推進する予約システムなど拡張性の高いシステムになるため、オペレーションや人員配置に合わせた最適な運営が可能になります。
属人的になりがちな精算やチェックイン業務をシステム化し、スタッフによる施設案内やおもてなしの時間に充てることで宿泊体験の向上と人手不足の解消を実現いたします。

まとめ
地域の魅力を高め、観光客の満足度を向上させるためには、個々の企業の努力に加えて、旅館組合や観光協会といった連携組織の活用が不可欠です。また、地域の飲食店や小売店、体験型サービス事業者との連携を強化し、旅行者と地域住民の交流を促進することが、地域全体の付加価値向上に繋がります。近年、旅館業界では倒産や廃業が増加しており、M&Aは事業継続や経営改善の有効な手段の一つとなります。特に人手不足の解消や施設のリニューアルに必要な資金調達の面で効果が期待されます。
今後は、伝統的な旅館の魅力を守りつつ、DX化や新たな発想を取り入れ、変化する市場や顧客ニーズに対応していくこと、そして地域全体が一丸となって観光地域づくりに取り組む姿勢 が、観光立国としての日本の発展に大切になってくる要素なのかもしれません。